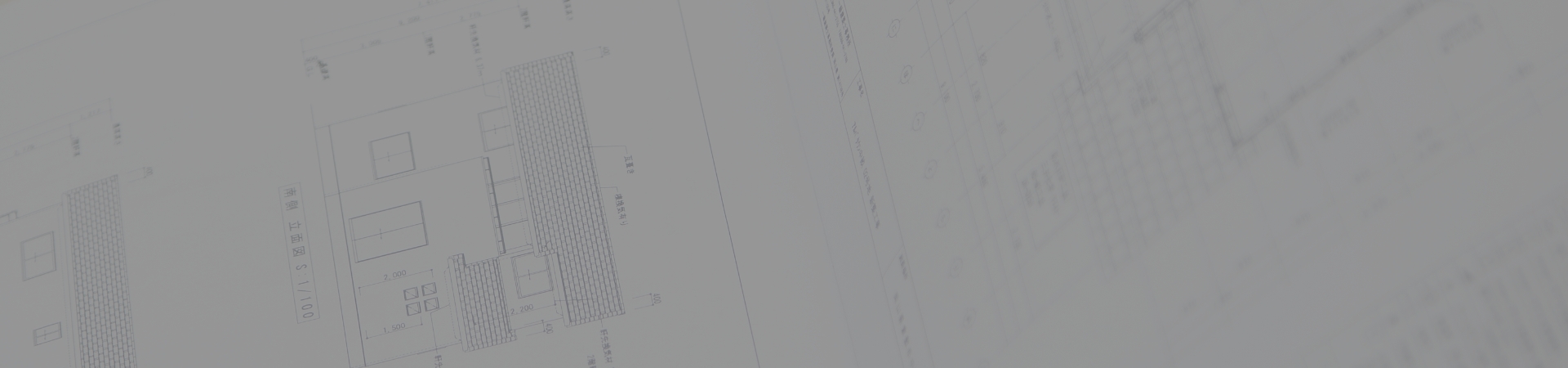
Webマガジン
2020/11/09コラム
江戸間と京間。

書院に違い棚、黄金の天袋に白銀の地袋と王道な画像ですが・・・今回は畳みについて語ります。
と、言う訳で・・・カテゴリーをコラムにしてみました。
(実は画像のお部屋も弊社アルバタウン児島の一部屋となります)
結構有名な話ですが、関東と関西では畳の大きさが違います。
江戸間(176cm×88cm)と京間(191cm×95.5cm)に分かれます。
他、中京間や団地間が有名ですが、岡山では六一間(185cm×92.5cm)が多かったみたいですね。
江戸と京都で畳みの大きさが違うのは、柱間が違うからです。
京都の町家は狭い家が多く、もともと柱の内側の寸法が決まっていて
それに合わせて部屋をつくっていたので、畳の大きさも自然に決まっていたんですね。
結果、大きさが決まっていれば使い回すことができるので、合理的なのです。
確かに柱の芯で畳の大きさを決めたら、柱の太さが変わったときに使い回せなくなりますよね?
便宜上、全国的に多いのは江戸間だそうで、国土交通省が発表している『住生活基本計画』の資料によると、
健康で文化的な住生活を送るために必要不可欠な最低限の面積は、単身者世帯で、25㎡必要とのこと。
つまり、畳の大きさに換算した場合、江戸間で16畳必要なんですね。
因みに、理想的な生活を送る(目安)には単身世帯で40㎡必要で、畳換算26畳必要ということになるのです。
理想的で豊かな生活ができる広めな単身住宅をご希望の方、
畳み部屋はございませんが・・・『六角形のお部屋』など如何でしょうか?
と、言う訳で・・・カテゴリーをコラムにしてみました。
(実は画像のお部屋も弊社アルバタウン児島の一部屋となります)
結構有名な話ですが、関東と関西では畳の大きさが違います。
江戸間(176cm×88cm)と京間(191cm×95.5cm)に分かれます。
他、中京間や団地間が有名ですが、岡山では六一間(185cm×92.5cm)が多かったみたいですね。
江戸と京都で畳みの大きさが違うのは、柱間が違うからです。
京都の町家は狭い家が多く、もともと柱の内側の寸法が決まっていて
それに合わせて部屋をつくっていたので、畳の大きさも自然に決まっていたんですね。
結果、大きさが決まっていれば使い回すことができるので、合理的なのです。
確かに柱の芯で畳の大きさを決めたら、柱の太さが変わったときに使い回せなくなりますよね?
便宜上、全国的に多いのは江戸間だそうで、国土交通省が発表している『住生活基本計画』の資料によると、
健康で文化的な住生活を送るために必要不可欠な最低限の面積は、単身者世帯で、25㎡必要とのこと。
つまり、畳の大きさに換算した場合、江戸間で16畳必要なんですね。
因みに、理想的な生活を送る(目安)には単身世帯で40㎡必要で、畳換算26畳必要ということになるのです。
理想的で豊かな生活ができる広めな単身住宅をご希望の方、
畳み部屋はございませんが・・・『六角形のお部屋』など如何でしょうか?
